私は幼少期の約10年間をアメリカで過ごしました。その時の経験を踏まえ、私なりに感じたアメリカ文化について共有できればと思います。他の国の文化を知ることで、自身の生活にその考えを取り入れたり、改めて日本の文化の良さを知ることができると思いますので、ぜひ読んでみてください!
今回はアメリカの部活について共有していきたいと思います。部活といっても、基本的にはスポーツが中心であり、それも時期(シーズン)ごとに変わります。さらに、その部活に所属するためにはトライアウト(選抜試験)に合格する必要がございます。なぜこのような仕組みになっているのか、またその良し悪しについて一緒に考えていければと思います。
時期(シーズン)ごとにスポーツが異なる
アメリカでは学校の部活は中学校から始まり、高校生から本格化していきます。特に中学生の時は日本のように部活が多彩にあるのではなく、選択肢は主にスポーツのみとなっており、それも年中同じ部活に所属するのではなく、時期(シーズン)ごとに区切られております。時期が変わるとスポーツも変わる仕組みになっております。
例えば私の中学校(ミドルスクール)では、以下のようになっておりました。
| 季節 | 男子 | 女子 |
| 秋 | アメリカンフットボール クロスカントリー(長距離走) | チアリーディング バレーボール クロスカントリー(長距離走) |
| 冬 | バスケットボール | バスケットボール チアリーディング |
| 春 | ラクロス 陸上 サッカー | グラウンドホッケー 陸上 サッカー |
| 夏(学校は休み) | 野球 | ソフトボール |
※夏は新学年に向けた長期休暇となっております。
私の場合は秋にアメリカンフットボール部、冬にバスケットボール部、春に陸上部、夏は学校とは別に野球をやっていました。このように、1年を通して複数のスポーツを経験する機会があります。皆さんもご存じの通り日本の部活動は基本的に年中活動しているため、大きな違いがあります。
時期(シーズン)ごとにスポーツが異なる背景と評価
背景や良し悪しの評価については私の個人的な意見になりますが、以下考えられます。
<背景>
- これら部活の時期は基本的にプロや大学のスポーツチームの時期と同じタイミング。アメリカ人の感覚でこのスポーツの時期やこの季節というのがはっきりしているため、部活動でもそれに合わせている。
- 複数の部活・スポーツを経験する機会を与えている。
- 同じスポーツを継続した場合、身体の一定箇所に負荷がかかり続けるため、ケガにつながりやすい。ケガを予防する観点で年中同じスポーツをすることを避ける。
<評価>
良い点
- 複数のスポーツを経験することで、自分に合うスポーツを見つけることができる。
- 複数のスポーツを経験することで身体の動かし方をより理解できる。
- ケガの可能性を下げることで、選手が長い間、楽しみながらスポーツができる。
悪い点
- 部活は一つのシーズンのみのため、年中同じ部活に所属する人に比べて専門性が育ちにくい。また、次のシーズンまで期間があくため、身体の動かし方を忘れてしまう。
トライアウト制度
もう一つ日本と大きな違いはトライアウト制度です。上記羅列した中学の部活動の中で、トライアウト制度を設けていないのは大人数が参加できる協議であるアメリカンフットボール、クロスカントリー、陸上のみでした。それ以外の競技はすべてトライアウト制度を導入しており、受かった人たちだけが部活動に参加できます。(そのため、部活に所属している人は学校内で一定の尊敬を得られます。)
トライアウトにはどの生徒でも申し込みができるため、競技にもよりますが70-100人近くの人が集まります。トライアウト期間は申込者が一斉に呼ばれ、数日間~1週間ほどかけて選考を行っていきます。評価者はコーチ陣であり、3~4人のコーチが分担しながらトライアウトをリードしていきます。
まずは人数をある程度絞るため、基礎運動能力やその競技の基礎的な練習メニューを実施します。トライアウト期間にもよりますが、大体その日の結果が翌日学校で張り出され、選考が進む連れて人数も徐々に人数が絞られていきます。そして人数が絞られるにつれ、より実践的な内容になっていきます(最終的には紅白戦など試合形式で行います)。トライアウト最終日まで誰が合格するのか分からないため、常に緊張感があります。競技にもよりますが、最終的には試合に必要な人数の2倍~3倍くらいの人数に厳選されます。例えば野球であれば18人(9人で試合をする)、バスケットボールであれば15人(5人で試合する)となります。
あるトライアウトの具体例(バスケットボール)
1日目:参加者100人 反復横跳び、垂直飛び、シャトルラン等基礎運動力テスト。バスケ基礎連もある。
2日目:参加者60人 パス、ドリブル、シュートの練習メニュー。実践は3オン3(少人数での実践)
3日目:参加者40人 2日目と似たようなメニュー。最後にはハーフコートでの5オン5(半面での実践)
4日目:参加者30人 より実践に近い。コーチから具体的な動き方の指示があり、その実行・理解などが見られる。
5日目:参加者22名 実践形式継続。練習後、最終合格者確定。
トライアウト制度の背景と評価
こちらも私の個人的な意見ですが、以下考えられます。
<背景>
- 人には向き不向きがあり、不向きなことを継続してやらせることは良しとしていない。それよりその人ができること、輝ける場を見つけてあげる方が良いとされている。
- 練習時間が限られており、効率重視。2~3時間といった限られて時間で効率の良い練習をするためには、厳選されたメンバーで練習を行った方が効果的。
- コーチたちは教えることは投資だと思っている。基本的には試合に出れそうな人、活躍できそうな人に教えた方が費用対効果が高く、コーチにとってもメリットを感じる。補足すると、コーチも教え子が活躍したり、チームが良い成績を残すと中学校から高校へと活躍の場が広がる可能性がある。
<評価>
良い点
- 試合に出れる見込みがある選手のみ最初から厳選しているため、選ばれなかった人は違う道でより輝く場所を探すことができる。
- 競争社会、実力社会であることを学生のときから自覚させてくれる。
- 実力主義の世界において、トライアウトのような限られたチャンスで成功を掴むためには事前準備が重要であることを教えてくれる。
悪い点
- 成長があまり考慮されていない。本来受からなかった人でも、成長して活躍できた可能性はゼロではない。
- チームのために、という自己犠牲の精神が生まれにくい。日本のように試合で活躍できない人も部活のために何ができるか考えるなど自分で活躍できる場を模索できる。
個人的に感じること
時期(シーズン)ごとにスポーツが異なること、そしてトライアウト制度はともに学生に複数の選択肢を提供し、自分に合うものを見つける機会を提供してくれると感じました。なかなか日本の部活では「これは向いていないから違うことをした方がいい」と面を向かって言われることはないと思います。(ひと昔前は指導者もかなり強かったので、あったと思いますが、、)ただ、これは必ずしもマイナスではなく、本当に合わないのであればそこで努力するより別の分野で努力した方が自分にとって良い結果をもたらしてくれるかもしれません。例えば野球が好きだが運動音痴で、実は将棋の才能がある人がいたとします。彼は頑張って野球を続けるより将棋をした方が才能が開花するかもしれません。その結果、将棋のプロになれるかもしれませんし、そうではなくても、野球をしている頃より優秀な成績を上げ、より自分に自信を持てるかもしれません。
さらに、トライアウトに落ちたが本当に諦めきれない場合は来年受かるようもっと頑張ろうと思うかもしれない。トライアウトに向けた準備として外部指導に申し込んだり、自主練をしたりするなど、チャンスをものにするための工夫をするかもしれません。また、諦めきれないということはそれが自分は本当に好きなんだと気づけたりするかもしれません。
これらを考慮すると、個人的には部活動でもトライアウト制度を導入しているのは良い仕組みだと感じます。学生個人の才能・能力をいかに発見し開花させるか、このような精神がアメリカ社会にはあると感じました。
最後に
今回はアメリカの部活動事情について説明させていただきました。時期(シーズン)ごとにスポーツが変わることやトライアウト制度を通して学生に複数の選択肢を提供し、これらが結果的に学生個人の才能・能力を発見する一助になると感じました。日本の場合は「石の上にも3年」というように、すぐに芽が出なくても継続して鍛錬を積んでいくことが美徳とされ、部活動の精神もこれに基づいていると思います。日本流も学びが多いと感じていますが、アメリカ流の効率的に努力の方向性を定めることも掛け合わせるとよりよくなると感じました。一度自分自身を見つ直し、今やっていることが本当にあなたに向いていることなのか、好きなことなのか、改めて考えるきっかけになればと思います。
無限に発展する道はいくらでもある。要はその道を探し出す努力である。
松下幸之助 パナソニック創業者
では、また。ゆとりのある日々を。
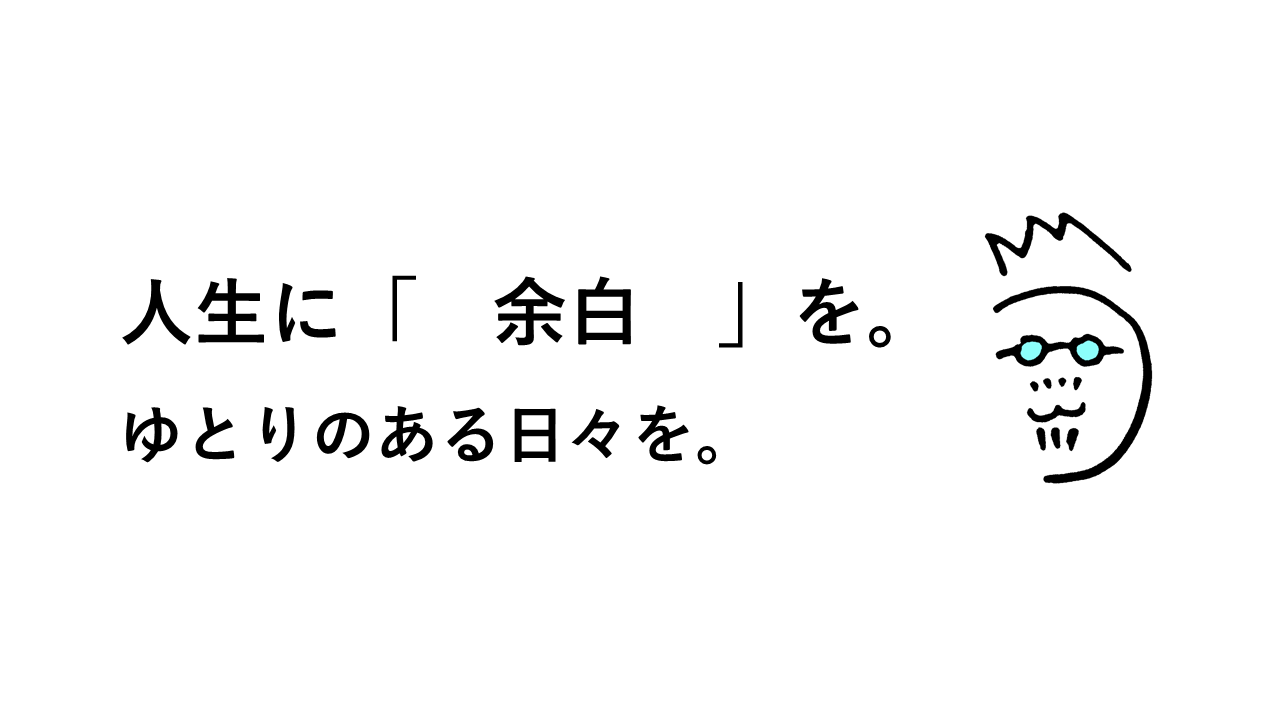



コメント