日々のやらなければいけないことに追われたり、いつの間にか固定観念が出来上がり視野が狭くなったり、自身の“当たり前”が形成されていたり。日々生活する中で、我々は意識しようとしまいとこのようなことが起きていると思います。それらを認識し必要に応じて見直すためにも、時折自身の考えを客観的に見たり、今までとは異なる考え方に触れ視野を広げることが大切だと感じます。その結果、自身の許容が広がり(すなわち余白が広がり)、心が広くなると言えます。今までは許せなかったことを許せるようになったり、ちょっとしたことで怒らなくなる・イライラしなくなると思います。
ここでは私が過去出会った人、本、映画、体験などで余白が広がった経験を共有できればと思います。今回私が紹介するのはヤーコプ・ファン・ユクスキュル作「生物から見た世界」という本についてです。
あらすじ
ヤーコプ・ファン・ユクスキュルはドイツの生物学者・哲学者であり、彼が提唱した環世界の概念は生物学のみならず哲学にも影響を与えました。1934年に出版された「生物から見た世界」はユクスキュルが環世界について書かれた本として最も有名です。
生物がそれぞれ独自の知覚世界を持っていること、すなわちそれぞれ環世界を持っているとしています。そして、生物の行動は刺激に対する物理反応ではなく、環世界によって形成されていることを示しています。簡単に言うと、主体(それぞれの生物)は自身が主観的に作り上げた”目”を通して世界を見ていることになります。この説明を聞いても何のことか全く想像がつかないと思うので、いくつか本で紹介されていた具体例を以下共有します。
時間の概念について
人間にとって一瞬とは1/18秒のことを指します。何故かというと、人間の目は1/18秒より速い映像を処理できず、1/18秒より速い世界を認識することができないためです。一方、カタツムリにとっての一瞬は1/4秒です。この差により、人間から見たらカタツムリはのろいな、と思っても、それぞれの生物が感じる“一瞬”は同じであると言えます。別の生物としてダニを例に挙げると、ダニは獲物が来るまで待期期間に入り何年に渡って停止できることから、ダニにとって時間の概念は存在しないとも言えます。
設計された反応
ウニの場合は、外部からの刺激がある反射的に反応し、とげが出るようになっています。蛾の場合は、高い音がするとすぐに飛び立ちます。それぞれ生物としての生存・防衛のために、遺伝子レベルで設計された行動です。逆に言うと、蛾は高い音が聞こえると鳥に襲われたという”人生”経験をしたから飛び立っているのではなく、遺伝子的に反射するよう設計されていると言えます。
人間の場合はトーンが設計されており、あるトーンと行動を結びつけることで学習していきます。例えば椅子。これは座るものだと学び、座るトーンが出来上がります。このトーンは拡大可能であり、同じ椅子でも、モノを置くトーン、誰かを攻撃するための武器としてのトーン、など多岐にわたります。当たり前だろ、と思うかもしれませんが、人生で一度も椅子を見たことがない人にとって、それは何のために存在するのか想像が難しいと思います。もしくは今のスマホ世代の子供たちがカセットテープを見たら、もしくは19世紀の人がスマホを見たら、何をするものか想像が難しいはずです。このように、何かを見て学ぶことでトーンが蓄積され、人間として学習するよう設計されているのです。
人間の生まれ持った性質はハンス・ロズリング作「ファクトフルネス」という本で数多く紹介されているので、興味がある方はこちらもご確認ください。
| FACTFULNESS(ファクトフルネス) 10の思い込みを乗り越え、データを基に世界を正しく見る習慣 [ ハンス・ロスリング ] 価格:1,980円(税込、送料無料) (2025/4/24時点) 楽天で購入 |
このように、生物はそれぞれ環世界を持っており、それぞれの環世界という主観を通して物事を知覚していることが分かります。時間という物理概念はすべての生物にとって平等ではなく、知覚の仕方によって異なるのです。また、何かをしたいから行動するのではなく、遺伝子に組み込まれた反射の結果が行動に現れることがあることもわかりました。
余白が広がる瞬間
この本の中で最も印象的だったことは生物によって時間の概念が異なるということです。人間が感じる一瞬とカタツムリが感じる一瞬は異なり、他の生物にとってもこのような時間感覚は異なると言えます。個人的に時間の概念は皆同じであり、客観的な数字であると思っていましたが、それは人間が観測した世界において同じである、という前提がありました。時間は客観的なものではなく、それぞれの生物から見た環世界によって観測されているものでした。
こちらの本では生物ごとに環世界を持っていると説明されていましたが、考えてみると人間同士でも、異なる環世界を持っていると言えます。全く同じ人生を送ってきた人はいないため、誰しもが独自の環世界(主観)を持っており、それはすなわち客観的・周知の事実だと各々が感じていることは人によって異なると言えます。その人が今までどのような経験・体験をしてきたか、どのような知識を身に着けたかによって独自の環世界が出来上がり、世界を知覚する“目”は気づかないうちに固定概念というフィルターを通して物事を見ていることになります。
上記前提に立つと、自分以外の人と100%分かり合うことは不可能であると言えます。そして、言葉という共通項を使いながら、お互いの見ている世界を理解し、折り合いをつけながら共存しているのです。相手が自分の思うように行動してくれない、相手が自分をわかってくれないと嘆くのは実は無理なお願いなのかもしれません。もし自分の考えが相手に伝わっていないのであれば、それはお互いの環世界の離れ具合を埋めるほどのコミュニケーションを取れていないということです。
また、人間の環世界は物事のトーンの蓄積でできていると言えます。例えば椅子は座るものとして生きてきた人と、椅子は武器として生きてきた人では知覚する世界がすでに異なります。もしそうなのであれば、我々は蓄積するトーンを増やすことで自身の環世界を広げることができます。すなわち、より多くのことを経験することで、より多くの物事を認識でき、色んな人とわかり合う余地が広がるのです。何かを学んだ途端、今まで見ていた世界が広がった経験はありませんか?例えば私の場合は革靴に興味を持ち調べるようになってから、電車の中で色んな人の靴が目に入るようになりました。今まで見ていたはずだが認識していなかった革靴を、ある時点から認識できるようになったのです。自身の環世界にないもの、既存価値観にないものと触れ、それを自分のものとして取り込むことで環世界を広げることが大切であると改めて理解することができました。
最後に
今回はヤーコプ・ファン・ユクスキュル作「生物から見た世界」という本について紹介させて頂きました。ぜひ興味がある方は手にとって読んでみて頂ければと思います。
| 生物から見た世界 (岩波文庫 青943-1) [ ユクスキュル ] 価格:858円(税込、送料無料) (2025/4/24時点) 楽天で購入 |
世の中には客観的な事実はなく、あくまで各々の主観的な“目”で世の中を知覚しており、その“目”で物事の客観性を判断していることが分かりました。そして、その“目”は各自の過去の経験・体験・知識によって出来上がっています。このように、我々が考える常識・当たり前のようなものは気づかないうちに出来上がっており、各人の固定概念として形にいます。
人間同士でも分かり合えないことがたくさんあるからこそ、人との交流を大切にし、共通項を見つけたり、自身の世界を広げる努力を継続していただければと思います。
我々はすべて異なる「環世界」で生きている
ヤーコプ・ファン・ユクスキュル ドイツ生物学者・哲学者
では、また。ゆとりのある日々を。
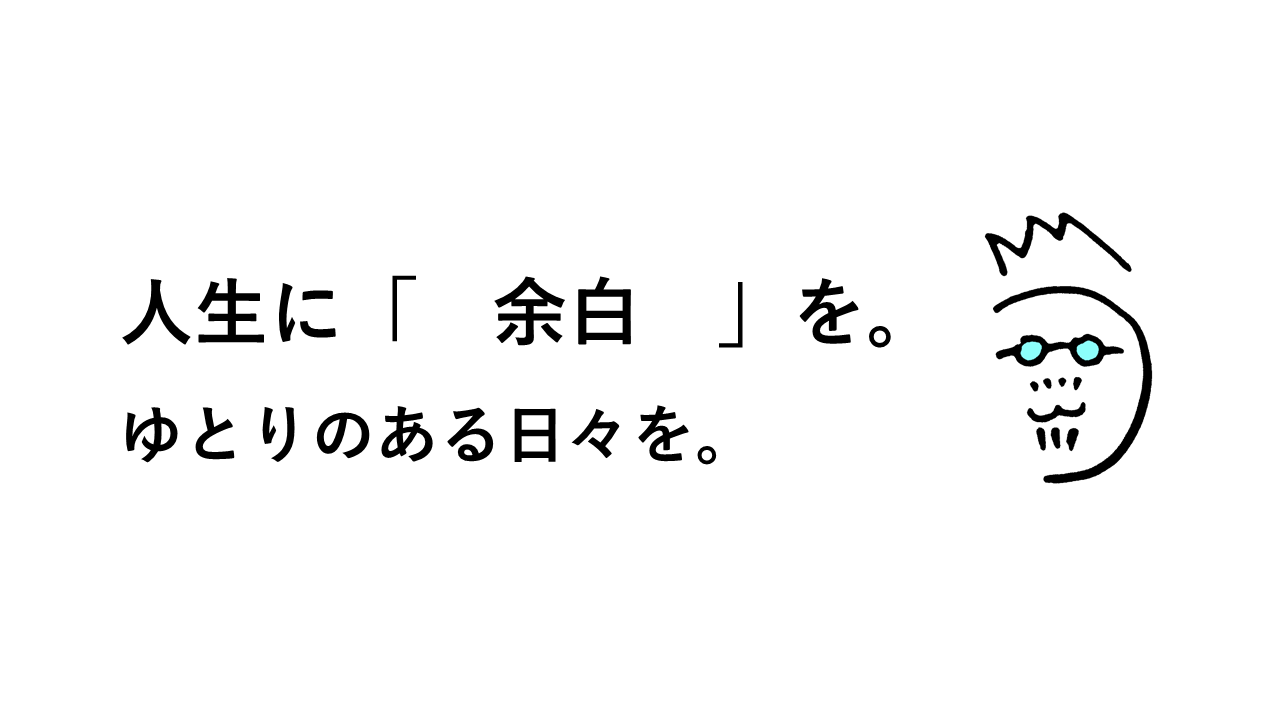



コメント