私は幼少期の約10年間をアメリカで過ごしました。その時の経験を踏まえ、私なりに感じたアメリカ文化について共有できればと思います。他の国の文化を知ることで、自身の生活にその考えを取り入れたり、改めて日本の文化の良さを知ることができると思いますので、ぜひ読んでみてください!
今回は私と私の家族が実際に経験した情報社会の実情を共有していきたいと思います。アメリカは自由な国であり、アメリカンドリームを掴むチャンスが皆にあると言われています。一方、その機会を掴むチャンスは平等ではないと感じています。その大きな理由が一部のコミュニティにしか共有されない情報があるためです。このようなアメリカの情報社会の実態把握と、これが果たして悪いことなのか、一緒に考えていければと思います。
教育(公立学校)における情報格差
私が現地校の公立学校に通っていた際、毎年のクラス分けは生徒のレベルに応じて行われていました。現地校の小学校・中学校と、その学年で成績が優秀な生徒は優秀な先生のところに振り分けられていました。そのため、授業を進めるスピードも各クラスで異なっていました。
ただし、このクラス分けの意図は公表されておらず、普通に生活していると気づきにくいと思います。
子供たちはわざわざ別のクラスの友達と授業の内容について話すことはなく、そもそも同じクラスの子たちと自然と仲良くなっていくため気づきにくいです。また親としても、授業は同じスピードで進んでいると思うと思いますし、先生や子供からこのような話を聞かない限りわかりにくいと思います。私の場合は兄弟が同じ公立学校に通っており、クラスによって異なる授業環境だったということを親が気づいたことで発覚しました。
さらに、クラス分けのみならず、能力が高い生徒に向けた特別授業もありました。私が小学校の時、優秀な25-30人クラスの中でもさらに算数が得意な5人向けに特別授業が行われました。みんなが算数の授業を受けるとき、別室に5人が呼び出され、別内容の授業が進みました。さらに6年生の時には、クラス全体で6年生ながらも半年で6年生の算数を終わらせ、残り半年で7年生(中学1年生)の算数を勉強するといった内容でした(ちなみに、小学校で個別に呼び出された人の内、3人はここでも同じクラスでした)。そして、年度の最後に、7年生の数学の授業を飛び級するためのテストを受け、25人のクラスで、なんと8人が7年生の数学の授業を飛び級することになりました。
このように、能力が高い人にはさらに次のレベルの環境や授業内容を提供するといったことが公立学校でも当たり前に行われていました。繰り返しになりますが、このような個別クラスや飛び級するためのテストがあることなどは一般的に知られておらず、能力がある人にだけ話があるものでした。(アメリカの公立学校の詳細についてご興味ある方は以前書かせて頂いた記事を併せてご確認いただければと思います。)
スポーツにおける情報格差
次はスポーツにおける情報格差をご紹介します。
アメリカでは学校の部活は中学校から始まり、高校生から本格化していきます。日本のように部活が多彩にあるのではなく、主にスポーツのみとなっており、それも年中ではなく時期(シーズン)ごとにスポーツが変わる仕組みになっております。また、中学校では部活の数が限定的であるため、一部スポーツのみしか部活として提供していません。部活のスポーツ以外でも時期によってお金を払って参加するスポーツチームがあります。例えば、中学校までは野球は部活のスポーツとして存在しておらず、夏休み中の野球リーグに参加するのが一般的です。この野球リーグは希望者全員がお金を払えば参加することができます。
この後野球の事例を共有させていただきますので、もう少し夏の野球リーグについて補足します。野球リーグは基本的に2学年分で一つのリーグとなり、参加者は各チームに振り分けられます。人チームは大体12~13人となっており、全員がバッティングに参加でき、守備は自由に毎回交代できるようになっており、各自均等に手番が回るようになっております。(補足:野球は9人スポーツであり、上記は通常のルールではなく子供たちに均等の機会を与えるものとなっております。)一つのリーグには8チームほどあるので、年齢の近い学生約100人くらいで野球をやっているイメージです。
さて本題に戻りますが、この野球リーグとは別に、選抜チームも存在しています。このチームは地区に一つ存在しており、地区代表みたいなものです。対戦相手はその他地区代表であり、全員参加の野球リーグとはまた異なります。選抜チームに入るためにはトライアウト(選抜試験)があり、合格したものだけが所属できます。ただし、トライアウトの場所や日時の情報は一般公開されておらず、直接誘いが来た人だけに情報が共有されます。野球リーグで数年活躍していると、トライアウトに興味がないかと声がかかり、初めてトライアウトの情報が共有されます。一部野球好きは地区代表チームの存在を知っていますが、普通の野球リーグに参加している友達は地区代表チームがあることすら知られていません。
さらに、野球での活躍などは中学高・高校の部活スポーツにも影響します。例えばアメリカの学校の部活としてアメリカンフットボールがあります。この部活はほかのスポーツと異なりトライアウト制度(選抜試験があり、不合格の場合は所属できない)がありませんので、希望者は全員入部できます。(部活のトライアウト制度についての詳細が気になる方は過去書かせていただいた記事をご確認いただければと思います。)
日本の部活のように希望者が全員参加することができます。その代わり、人数も多いのでコーチが見ているチャンスでしっかり活躍できないと試合に出る機会がなかなか得られません。先ほど例に挙げた野球の地区代表に所属していたという情報はアメリカンフットボールのコーチの耳にも入っており、運動神経が良いと思われているので、コーチが気にかけて見てくれるチャンスが増えます。そこで結果を出すことで試合に出る機会が増え、さらに巡り巡って次の部活のコーチの耳にも情報が入ります。
このように、スポーツにおいても情報が一部の人にしか伝わらず、また知らないところで自分の情報が広まっていたりします。結果的に、能力がある人はチャンスがどんどん増える仕組みになっています。
個人的に感じること
実力・能力があることを結果で示せた人はその分次のステージが用意され、さらに能力を伸ばす機会が与えられます。一方、知らない場合は知らないまま、その人は今の生活に満足すると思います。このように、各人のレベルに応じた環境を提供するのがアメリカ流だと感じました。能力が高い人はより競争的で高いレベルを求められる環境が用意されていく一方、そうではない人は似たような能力の人が集められた環境で楽しむことができます。
さて、ここで良し悪しについて考えてみたいと思います。
<良い点>
- 能力が高い人はレベルをより高められる。能力が高い人が集まるため、切磋琢磨して全体のレベルも引き上げられるし、その中で突出した人はさらに次のステージに進む機会がある。
- 似たような能力の人が集まるため、劣等感を抱きにくい。
- それぞれのレベルにあった環境で伸び伸び成長することができるため、自己肯定感が高い人が多い。
<悪い点>
- 能力の差がどんどん広がっていくこと。最終的にこの差は収入・所得差に広がると考えられる。
- 一度「あなたは○○のレベル」とレッテルを貼られるとそれを覆しにくい。環境が異なるため上がる機会が少なくなるのと、自分自身を奮い立たせて頑張ろうという気持ちがわきにくいため。
- 能力が高い人のレールを歩む人は常に競争にさらされると感じる。頑張り続けないと勝ち組みレールからふるい落とされる危機があると感じている。
できる人をより良くするため、すごく優秀な人が生まれるようになります。しかし格差はどんどん広がってしまう仕組みであり、必ずしもいいところだけではないと思います。個人的には各人に適した環境を提供する仕組みは全体として幸福感が高くなるため、良い仕組みだと感じました。一方で、情報が限定的であったり、知らないところで情報が共有されている点については少し怖さを感じます。今ではSNSが広まり情報が以前より拡散されているため、全く知らないということはないと思いますが、根本的な仕組みは変わっていないと思います。
最後に
今回はアメリカの情報格差社会について説明させていただきました。この社会の結果として、各人に適した環境が提供されており、それぞれが幸福感を感じられる仕組みになっていると感じました。アメリカではこのように自身に適した環境を周囲が提供してくれる社会になっていますが、日本においては自身で環境を変える努力が必要になると思います。現在の環境が自分に適しているのか、改めて見直すきっかけになればと思います。
自分の能力以上を求められる環境でなければ、個人の成長は難しいんです。
柳井正 ファーストリテーリング創業者
では、また。ゆとりのある日々を。
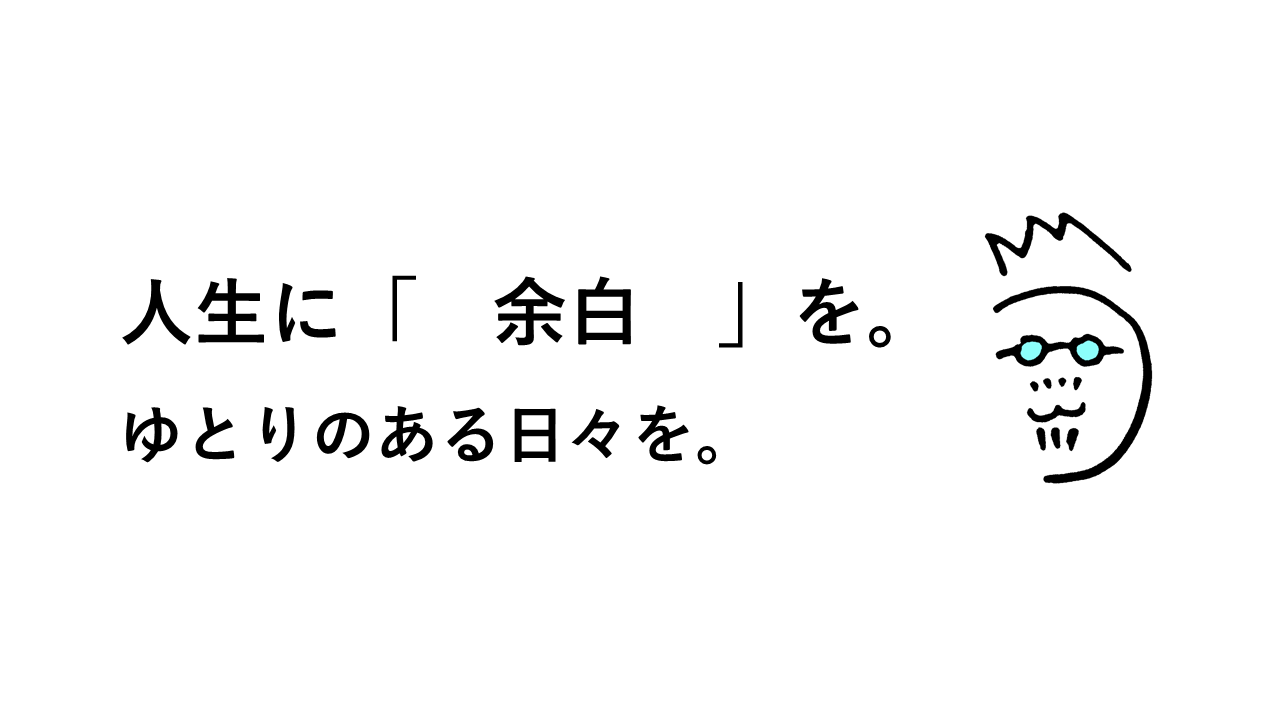
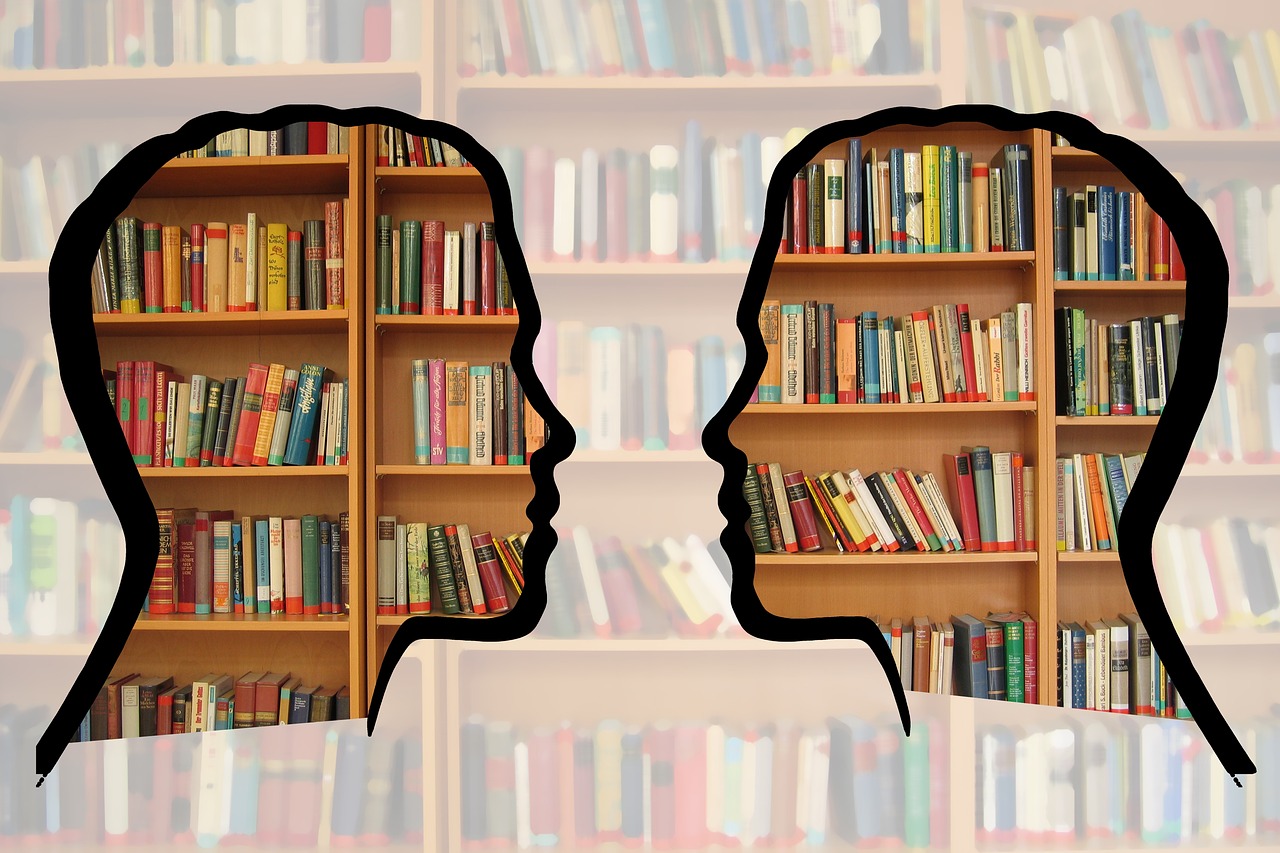




コメント