私はただいまベトナムに滞在しており、仕事を通してベトナムの文化や人々と触れております。日々過ごす中で、私が個人的に驚いたこと、面白いと思ったことを共有できればと思います。他国の文化・様子を知ることで、自身の生活にその考えを取り入れ日常が少し豊かになったり、改めて日本の良さを知ったりするきっかけになると思いますので、ぜひ読んでみてください!
今回は「良いものを積極的に取り入れる文化」についてお話したいと思います。ベトナム人は “良い“と思ったものは積極的に取り入れ、変化を恐れない傾向があると感じます。このような場面はあらゆる場面で目撃しており、今のベトナム文化を作り上げていると感じます。どのような場面でこの文化を目撃できるかご紹介したいと思いますが、正直日本人として「え?」と疑問に思う点も多々あります。一方、積極的に変化を受け入れることの良い面もあると思います。今回の記事が皆さんにとって、今よりもう少し変化を許容できる気づきにつながればと思います。
良いものを積極的に取り入れる文化
さて、ベトナム人は“良い”と思ったら何事でも積極的に取り入れる傾向があると書かせて頂きました。もう少し肉付けすると、ベトナム人は全体感を気にせず“良い”と思ったら何事でも積極的に取り入れる傾向があると思います。これだけ言われてもイメージが沸かないと思いますので、まずは以下の具体的な場面をご確認いただければと思います。
場面①街並み

ベトナムでは路面店が未だ多くあります。
道路沿いにお店が並んでおり、その光景が街並みを作っているとも言えます。ただ、どのような店が出店するか、どのような外観にするかなどは統一されておらず、出店するオーナー次第というところがあります。
ですので、少し汚いお店の間にポッとおしゃれなお店があったり、その逆でおしゃれな通りなのに汚い個人商店のお店があったりします。

街並みの外観としては統一感がなく、がちゃがちゃした印象を与えてしまいます。これはホーチミン市というベトナムの大都会で見られる光景です。
一方、日本の大都会では街並みが統一されています。
例えば東京駅付近はビルと洗練された空間、昔ながらのレンガの建物がおしゃれにリノベーションしてあり全体に統一感があります。京都や奈良などの街並みは昔ながらの建物・街並みを残しながら統一感を演出しております。だれが音頭をとって全体の統一感を演出しているか分かりませんが、日本の街並みは総じて統一されています。

ただし、ここで一言付け加えると、ベトナムの街並みが統一されていない理由はその地域に住んでいる人の要望もあってのことだと思います。
その地域の住民に利用してもらい商売を繁盛させるために柔軟に変化するため、街の統一感を待っていられないという点があるのかもしれません。
そしてニーズがあればすぐに変化していくので、より洗練されたおしゃれなお店が日に日に増えていると実感します。もしかすると、日本のように統一された街並みが出来上がるのは時間の問題なのかもしれません。
場面②お寺・仏像
ベトナムは仏教が主要の宗教となっており、人口の約7割が仏教徒であると言われております。ただ、感覚的には日本に近いと思っており、普段はそこまで信仰心があるわけではなく、年始などの行事にお寺にお参りに行ったり、お葬式が仏教式であったりという程度です。
話を戻すと、ベトナム人の多くは仏教徒であるため、ベトナム全土にお寺があります。地元の方々がに日常的にお寺を訪れることもありますが、基本的には観光地化されており国内外の人が訪れます。
そして、お寺を訪問すると、高確率で仏像の周りに電飾がついております。仏像の後ろには黄色やピンクの電球や電飾の光輪が飾られており、とにかくポップです。



日本人としては、このような装飾は仏教に失礼な行為のように感じますが、何故かベトナム全土のお寺でこのような光景を目にします。ベトナム人は電飾が好きなので、おそらく観光客がお寺を訪れる際に電飾の明かりがあった方が見栄えが“良い”と判断してのことだと思います。
しかし、仏教の考え方やお寺との統一感・整合性などを考えると本当にそのような装飾をつけていいのか、と疑問が湧きます。そこまで深く考えていないのか、それをひっくるめてもやるべきだという判断なのか、正直良くわかりませんが、とにかく“良い“と思ったら突き進むのがベトナム流だと感じる光景です。
場面③職場の事例
職場の事例ですが、ベトナム人は新しい技術にすごくオープンで、積極的に取り入れる人が多いと思います。
例えば最近ではAI(ChatGPT)が広まっていますが、ベトナム人スタッフはすぐにこのようなツールを職場で使っています。それも数名ではなく、大勢のスタッフが使っているのを目にします。
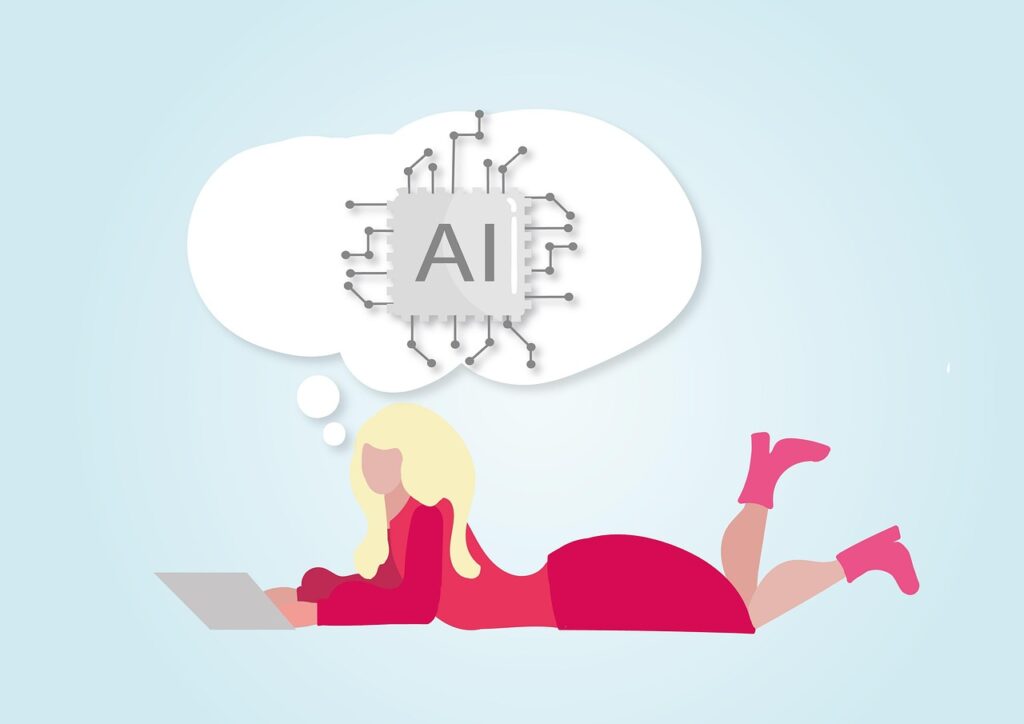
一つの要因は職場の平均年齢が日本と比較し若く、若い人は新しい技術を受け入れやすいというのがあるかもしれません。このように、ベトナム人は AIやあらゆるデジタルツールや考え方など“良い”と思ったツールを積極的に活用しています。このような柔軟性・スピード感は非常に良いと感じます。
一方、AIツールのリスクなどは特に考えていない人も多い印象です。このようなリスクもあるでしょ(例えば情報漏洩)と話をすると「え、そうなの?知らなかった」という人もたくさんいます。このように見切り発車で深く考えずに“良い”と思ったことを積極的に取り入れる人が多くいる印象です。
場面④食文化
ベトナムの食文化といえばフォーや生春巻きなど伝統的な米麺・米紙と野菜を活用した料理が多くあります。
それ以外にも、ベトナム北部では中国の影響(立地の近さ)や、全土ではフランスの影響(フランス植民地時代による影響)が多くみられます。中国の影響としてベトナム北部ではお茶文化が根付いており、食後に茶器でお茶をするシーンが良く見られます。

また、フランスの影響としてベトナム全土ではコーヒー文化が根付いており、朝や午後の夕方などカフェでたむろしている老若男女の姿を目にします。それ以外にもパンが美味しかったり、バインミーなどのパンを活用した料理もあります。

このように、異国の食文化が人々の生活に入り混じっています。そして、時間が経っても未だベトナムの食文化に異国の影響が色濃く見られるのはベトナムがそれら食文化を“良い”と判断したため残っているものであると言えます。
場面⑤模倣品
“良い“と判断されたものをいち早く真似して似たような製品を作ったり、本家レストランの隣に模倣レストランができる場合が多々あります。
分かりやすい例でいうと、ローカルレストランが挙げられます。店名と住所で口コミが広がりますが、本店の隣にほとんど同じ看板・同じ内容のレストランを出店し、住所もほとんど変わらないことから騙されて模倣レストランに吸い込まれるお客さんも多々います。
私も、口コミの高いローカルなお店に行ったときに、全く同じようなレストランが隣同士にあり、最初は同じお店が拡張しただけかと思いました。すると道端のおじさんが本物はこっちだ、と指を指して教えてくれました。
また、製品においても、一つの製品が人気になると、類似した製品を急激に増える現象が起きます。例えば、タピオカブームが起きたときには一瞬で街中タピオカ店が出始め、次に塩コーヒーが流行ると、こちらも一瞬で街中に広がります。流行が移り変わるスピードも速いですが、流行に対して敏感に対応した模倣品が世に出回るスピードもすさまじいと感じます。
(後編へ続く)
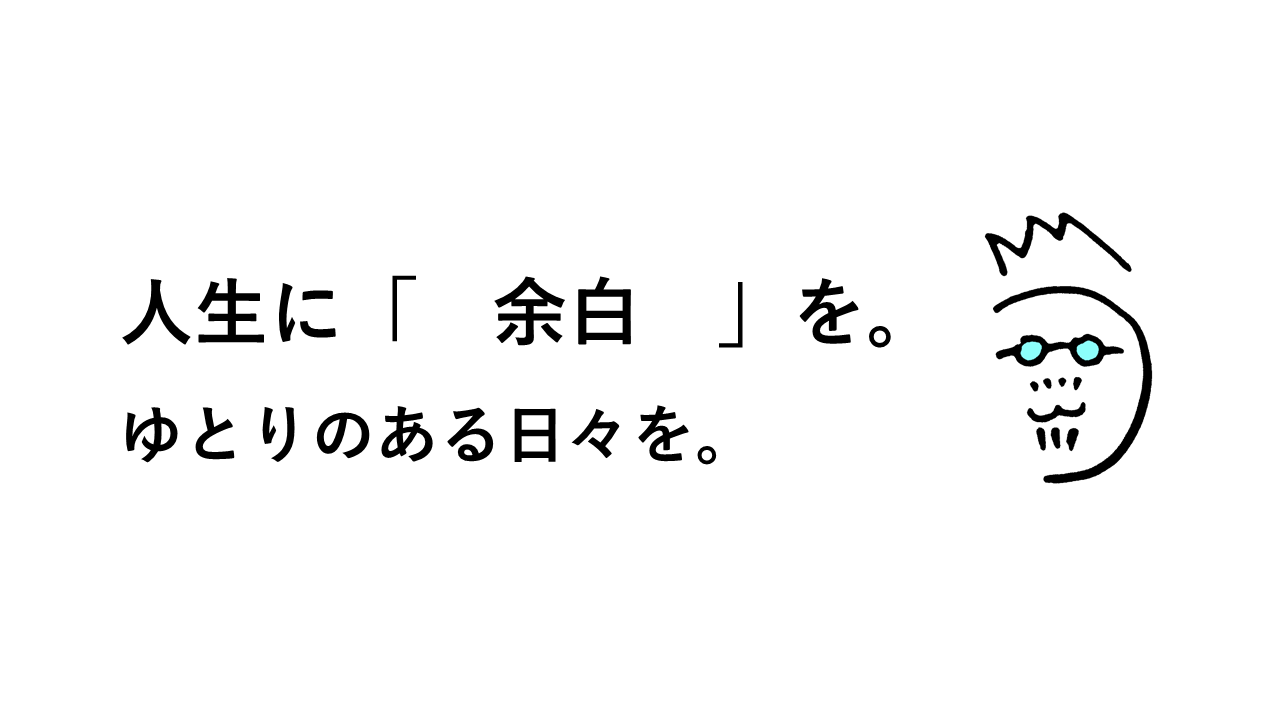




コメント