日々のやらなければいけないことに追われたり、いつの間にか固定観念が出来上がり視野が狭くなったり、自身の“当たり前”が形成されていたり。日々生活する中で、我々は意識しようとしまいとこのようなことが起きていると思います。それらを認識し必要に応じて見直すためにも、時折自身の考えを客観的に見たり、今までとは異なる考え方に触れ視野を広げることが大切だと感じます。その結果、自身の許容が広がり(すなわち余白が広がり)、心が広くなると言えます。今までは許せなかったことを許せるようになったり、ちょっとしたことで怒らなくなる・イライラしなくなると思います。
ここでは私が過去出会った人、本、映画、体験などで余白が広がった経験を共有できればと思います。今回私が紹介するのは近内悠太作「世界は贈与でできている」という本についてです。
あらすじ
本書は、経済活動や人間関係が「交換」によって成り立つと考えがちな現代社会に対して、「贈与(ギフト)」という視点を提示しています。贈与とは、見返りを求めず、純粋に他者へ何かを与える行為を指し、これが私たちの社会や人生を根底から支えていると著者は論じます。
近内氏は、哲学、宗教、文化人類学の知見を交えながら、贈与が持つ力や意味を探求します。例えば、親が子に与える無償の愛、他者への思いやり、自然から受け取る恵みなど、日常生活の中に潜む「贈与の連鎖」を明らかにし、これこそが私たちが豊かに生きる基盤であると示唆しています。また、資本主義や効率主義が支配する現代社会において、贈与が持つ可能性や課題についても考察し、「どう生きるべきか」という問いに対して一つのヒントを提示する内容となっています。
以下、本書で紹介されている贈与に関する内容を私なりにまとめたものとなります。
贈与の原理
- 贈与をする際に見返りを求めてはいけない
贈与する際に、渡した相手から見返りを求めることをしてはいけません。もし見返りを求めた場合は等価交換・ギブ&テイクの関係性になります(私がこれだけやったんだからあなたもやってよ)。この関係性において、何か交換することができなくなったときに、そのつながりは解消されることになります。
例:子育ての際に、子供に何かしらのリターンを求めているわけではないはずです。子供が無事成長できるよう愛を注いでおり、そこには損得勘定はないと言えます。 - 贈与は受け取ることなく開始することはできない
自分がすでに贈与を受け取っているからこそ、被贈与感・負い目に起動され、お礼として贈与は次々と渡されていくことになります。このように贈与は連鎖していくものです。もし自身が贈与を受け取っていないのに贈与をしようとした場合、それは自己犠牲になり、気づかずに自身が疲弊しすり減ってしまいます。
例:自身が子供を持ち子育ての大変さを身に染みて体感したときに、自分の親も同じように自身に対して大変な思いをしながらも育ててくれたことを理解できます。このように、最初に親からの愛情を受け取っているからこそ、自分の子供に対しても同じように愛情を注ぎ、育てたいと思えます。もし自身が親から愛情を受け取っていなかった場合、どこかの瞬間、なぜ自分は子育てにこんなに振り回されているのだろうか、なぜこんなに苦労してまで子育てをしなければいけないのかと自問自答してしまうと思います。 - 贈与には時間が必要である
贈与が手渡される瞬間に、それが贈与であると知られてはいけません。贈与であることを明示されると、その場で返礼の義務が生じ、その行為が交換となってしまいます。一方、ずっと気づかれることのない贈与はそもそも贈与として存在しません。これは当然だと思いますが、誰にも気づかれなければ誰も受け取った贈与に感謝せず、それを次に渡そうという想いにはなりません。必ずどこかのタイミングで相手にその行為が贈与だったと認識してもらう必要があります。このように、贈与を渡したときから、それが贈与だったと認識してもらうまで時間が必要であり、その時間があるからこそはじめて贈与が成立するのです。
例(贈与を知られてはいけない):子供に対して「あなたをこんなに頑張って育てている」「あなたの学費・生活費を誰が払っていると思うのか?」など発言して普段から贈与していることを見せてしまったとします。そうすると、その子は何かしらの形で受けた贈与を返さないといけないと思い、自分を押し殺してでも“良い子”で在ろうと演じてしまう可能性があります。
例(気づかれない贈与):あなたの家の周りの道路は常にきれいになっています。毎日そのような状態であり、それが当たり前だと思って生活をしています。ただし、実は家の周りの道路は毎朝近所の田中さんが朝4時に起きて掃除をしていました。この事実にずっと気づかず、あなたなその家から引っ越すことになり、結局田中さんが毎朝家の周りの道路を掃除してくれていたことに気づきませんでした。あなたは田中さんの贈与に気づかず、結果的あなたにとってこの贈与は存在しないことになります。 - 贈与には想像力が欠かせない
贈与を認識するためには、受け取る側の想像力が重要です。「あ、自分はこのような贈与を受け取っていたんだ」と過去の出来事を振り返りながら今に結び付けることで贈与を認識できます。逆に、もし自身が贈与に気づけなければ、贈与が存在しなかったことになってしまい、その贈与の連鎖はそこで終了してしまいます。さらには、贈与が届かない可能性が十分にあるからこそ、贈与の差出人になった際には「今から差し出す贈与がいつか気づいてくれたらいいな、届いてくれたいいな」と願うしかありません。
例:あなたは引っ越した先では家の周辺道路にはごみや落ち葉が落ちていることを目にします。今思えば、引っ越す前の家の周辺道路は落ち葉すら落ちておらず、非常にきれいでした。もう少し想像力を働かせて考えると、きっと誰かしら(市なのか個人なのか)が毎日道路を掃除してくれていたことが分かります。この時、あなたは以前受け取っていた贈与に気がつくことができました。
余白が広がる瞬間
私にとって、本書で紹介されている「贈与」という考え方に共感しました。そして、自身が今までどれほど贈与を受け取ってきたのか改めて認識することができました。実体験としては、例えば実家から出て一人暮らしを始めたときに、今まで母親が文句を一つ言わず、当たり前のように毎日食事を用意してくれていたありがたみを感じました。毎日食事を用意するだけでも大変なのに、健康にも気を使ったバランスの取れた食事や、子供たちが飽きないように毎日違う献立を考えながら用意してくれていたことに気が付くことができました。また、自身に子供ができ、子育てがいかに大変か身に染みて実感したときに、自分を育ててくれた親に対して尊敬と感謝の念が湧き出てきました。
そして、私は親から受け取った贈与を、自分の子供に対しても同じように渡したいと思いました。親から受け取った無償の愛を、今度は自身が子供たちに手渡す番です。まさに本書で紹介されている贈与の連鎖です。実際は、この本を読まなかったとしても贈与の連鎖は継続していたと思います。ただ、この本を読むことではっきりとこれが「贈与」であることを認識でき、より親から、友達から、周囲からの贈与を認識できるようになったと思います。さらには、今の現在が豊かで生活しやすい環境であることも先人たちからの贈与であると言えるのです。そう思うと、道端で咲いていた一凛の花にも感謝し、そのような光景が次の世代にも残るよう贈与の担い手になろうと意識できます。
また、私は贈与が何であるのかを理解することで、自分は相手に対して等価交換を求めているのか、それとも贈与を渡しているのか、意識するようになりました。もし等価交換であれば、見返りを求めるのは自然であり、それは最初からそのように伝えるべきです。そして贈与であるならば、それが贈与であることを言う必要がなく、いつかそれが贈与だったことに気づいてもらえればいいのです。すなわち、最初から自分には何も返ってこないと思っているからこそ、返礼を期待せず何もないことが当たり前となります。これらを混同してしまったときに、例えば贈与のように振舞っている(善意で何かをした)が、実は相手から何かしらの見返りを求めており、その返礼を受け取れないときにその人に対して嫌な気持ちになります。自身の中で等価交換か贈与かという整理をつけておくだけでも、自身の心を平穏に保つことができます。
例(等価交換):今からあなたにこの仕事の内容を教えます。これらをしっかり理解し、1か月後にはチーム員としてしっかり活躍してください。
例(贈与):(自分が先輩にしてもらったから、直接業務には関係ないが、新しく入った社員にも人生経験を積ませてあげよう)明日、○○部長も呼んで飲みに行こう。
例(贈与と等価交換が混同):あいつを何度も飲み会に招待しているのに、俺のことを全然尊敬しない。これだけ面倒を見ているなら、普通はお礼として飲みに誘ってくれたり、お歳暮の一つでも渡すだろ。
最後に
今回は近内悠太作「世界は贈与でできている」という本について紹介させて頂きました。ぜひ興味がある方は手にとって読んでみて頂ければと思います。
| 世界は贈与でできているーー資本主義の「すきま」を埋める倫理学 [ 近内 悠太 ] 価格:1,980円(税込、送料無料) (2025/5/12時点) 楽天で購入 |
あなたもすでに贈与を受け取っているはずです。一度立ち止まって、想像力を働かせながら過去に受け取った贈与を振り返ってみてください。そして、もしいくつか思いつくものがあれば、今度はその贈与を次の人へ渡してください。きっと人生がより幸福に感じると思います。
愛は、あなたが欲しいと望むこととは何も関係ありません。ただあなたが与えたいと望むことだけが全てです。
キャサリン・ヘップバーン アメリカ オスカー受賞女優
では、また。ゆとりのある日々を。
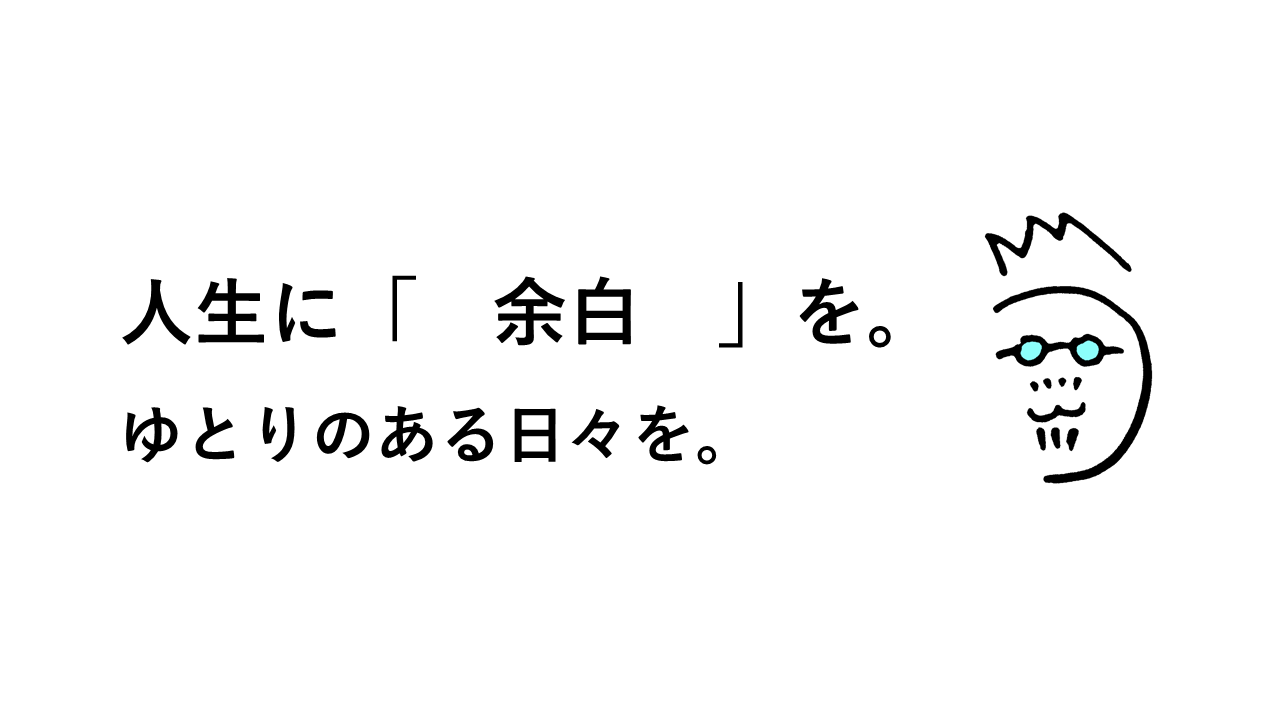



コメント